横山 彰人 著
第2章 町屋の家
咲子の生まれ育った家は京都市上京区西陣で、両親は高級織物で有名な西陣織を扱う小さな問屋を営んでいた。
西陣は江戸時代以前においてすでに一つの機業地として存在し、幕府の保護もあり、絹織物の産地として、歴史と伝統は古く、絶頂期には五千軒もの織屋があったという。
近年においても、戦争中及び戦後の沈滞期はあったものの、日本の復興、高度成長と共に西陣は益々隆盛を極めた。
その時代に咲子の両親は福井県武生から京都に出、人のつてもあって西陣織を手がける小さな問屋を始め、それなりに成功し何軒かの借家も持つようになった。
その後、バブル経済が破綻し、少子化や若い人の着物離れ、素材も合成繊維の安価な着物が出回り、今では西陣全体が低迷し、店を閉めたり、転業する家も多かった。
ここ十年の西陣の街並みも変容は激しく、子供の頃遊んだ路地や空き地はいつのまにか無くなったり、幼友達の家が駐車場やマンションになっているのを見るのは辛かった。
街を歩いている織職人や若い人もめっきり少なくなり、昔の活気はなくなったが、幼い頃からの遊び場だった北野天満宮の境内で開かれる縁日や、毎年二月初め、梅の花が咲くころ催される〝梅花祭〟の賑いは、昔と変わらず咲子は嬉しかった。
生まれ育った家は両親が問屋を始めたとき、もともと織屋をやっていた住まいを譲り受けた家だった。織屋が軒を並べる西陣の街並は、京都の街並みの中でも最も美しく、中京あたりの町屋とくらべると繊細さはないが、がっしりとした骨太の格子の町屋が並んでいる。
家の構造は町屋独特で、間口が狭く奥行が長く、家の片側が表から裏まで筒抜けの通り庭になっていた。父親が問屋を始める前に、一番奥の織を織る作業場を事務所に改造した。一階は通りに面して客間と仏間を兼ねた床の間付の両親の寝室があり、事務所と寝室の間に食堂兼茶の間があった。職住一体であり、部屋と部屋の仕切は襖で、寝る時以外はいつも開け放されていて、部屋の広さの割には広く感じられた。
一日の仕事が終ると、食卓にはいつも父と母がいて、働いている人も一緒に食事をし、家族団欒を共にした。
隣近所の人達や親しい仕事仲間の出入りも多く、いつも気楽に茶の間に上がりこみ、おしゃべりをしたり、時には勉強を見てもらったり、一人っ子の咲子であったが、寂しい思いをしたこともなく、今振り返ってもなつかしく幸せな思い出ばかりだった。
高校はバスで二回乗り継ぎ、西陣からは一時間と少しかかったが、京都市内が一望できるという理由とアカデミックな校風が好きで東山の中腹にある東山高校に通った。これといった部活もせず平凡な高校生活を送った咲子がなぜかお気に入りだったのは、誰もいないガランとした四階の教室の窓から、夕陽が洛西の西山に沈むまでの時間を過ごすことだった。
オレンジ色のグラデーションが京都の街を染めながら、やがて最後の一条の光を放って山の端に消えていく。眼下に見る暮れなずむ古都の街並み。東寺や本願寺の黒いシルエット。夕陽を見ているとクラスメイトとの人間関係やわずらわしいことも忘れ、優しい気持ちにしてくれた。
そしていつか結婚したら夕陽が見えるところに好きな人と住みたいと思った。
頭に浮かぶ家は、なぜか育った西陣の家ではなく、部屋にはサンサンと陽が入り、素敵な夕陽が見える近代的な高層マンションをいつも想像した。
三方を山に囲まれた箱庭のような京都の街の暮らしは、人と自然が寄り添って生きているようで大好きではあったが、高層マンションから見る街並は東京以外思い描けなかった。
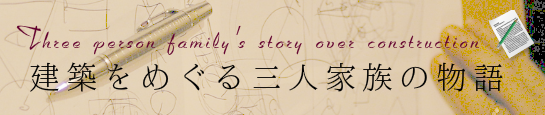
 第1章 無気力症候群
第1章 無気力症候群