横山 彰人 著
第24章 再生
咲子がいつもの時間に起きた時は、武夫はすでに出勤した後だった。テーブルの上には、昨夜の小児科学会のコピーと、眠れないままワインを飲んだグラスが、朝の日差しの中で白いテーブルクロスの上に影を落していた。
そしてそのグラスの横に、武夫の字で書かれた一枚の白い便箋が置かれていた。そこには端正な字で、「夕焼けには間に合わないけれど、今日は七時までに帰って来ます」とだけ書かれていた。
咲子は、黒のサインペンでしたためられた字を、どのぐらいの間見ていただろうか。そしてその一行の、たった二十八文字に込められた武夫の想いは、分りすぎるほど咲子には分った。二人を結びつけた夕陽、二人の大切な思い出として心に刻んだ数々の夕陽が、鮮やかに咲子の胸に蘇ってきた。
窓から見える海の色は、穏やかなスカイブルーを見せていた。咲子は、初めて海岸へ行ってみようと思った。海岸といっても自然の砂浜ではなく、お台場のように人工で造った小さな砂浜だと聞いていたが、ゆっくり歩いても十分ほどで行けるはずだった。
雑事に追われ、これまで行ったことは無かった。気が変わらないうちと思い、光と手早く朝食を済ませ掃除をし、ベランダの花に水をやり、光のおやつと簡単なおにぎりとお茶を用意し、海岸に行く準備をした。こんなに気持ちが弾んだのは、引越してから初めてのような気がした。
「光ちゃん、今日は海に行くからね」
「光ちゃんの好きなブルーの色、帰ったら海のお絵かきしようね」
と声をかけると、光は、「キャキャ」と言って、笑った。珍しいことだった。
海岸への道を、光をベビーカーに乗せてゆっくり歩いた。歩きながら、壁紙を貼ってくれたおじさんの話を思い出していた。埋め立てる前は海にたくさんの漁船が行き交っていたであろうこの場所が、今は乾いた住宅街が続いている。海を追われた家族はどこへ行ってしまったのであろうか。ひとつの街の歴史が消えて、新しい街の歴史が刻まれていく。
咲子はこの街をつくっていく一人になりたいと、ふと思った。
海岸は思ったより近く、腰を下ろす手頃な石を見つけ、光と並んで座った。初めて、海側から住んでいるマンションを見上げた。二十五階建てのマンションは、周りの建物が低いのでまるでランドマークのように建っていた。東京湾沿いに、お台場、葛西臨海公園、東京ディズニーランド、そしてこの地域をリゾートエリアと位置づけ、そんな街並を意識しているのかマンションの外観の色は、明るいベージュを基本色にオレンジやブルーで色分けされ、いかにも南欧のリゾート風の色合いだった。
見慣れた外観なのに、海側から見ると印象は随分違った。湾岸べりに隣接している遊歩道には、ワシントンヤシやソテツの樹が植えられ、ベンチの横の花壇にはサルスベリの花が咲いていて、その並びのパーゴラには蔓状に巻きついたノウゼンカズラのオレンジ色の花が咲いていた。なんとなく落ち着けて親しみの持てる雰囲気が、意外だった。
いつもベランダから見ている風景なのに、上から見下ろして見るのと下から見るのとは、視覚的にも心理的にも全く違うことがなぜか新鮮だった。咲子は、いつも遠くの風景ばかり見ていたような気がする。それは遠くだけを見て、足元を見ていなかったこれまでの日々と重なっていた。
海は真夏の強い日差しのころとくらべ、残暑がまだ続くとはいえ、もう空の色も海の色も秋のやさしさに満ちていた。南西の方には、京葉工業地帯の工場の煙突やアクアラインの銀色の帯が遠く霞んで見えた。アクアラインに沿って目を移すと、停泊中の貨物船やヨットが小指ほどに小さく見え、お台場辺りには建設用のクレーンが小さく白く光っていた。
海のもつ開放感と雄大な景色からか、昨夜のみじめな気持ちも癒され心も軽やかだった。
光は、おやつを食べ、いまは小石を拾っては海に向って投げ、投げる度にこちらを向いて笑っている。何がそんなに嬉しいのか。咲子もその度に手を振って笑い返すが、いつも光に心を見透かされているような気がして、戸惑ってしまう。目のあたりは武夫に、口元は咲子に似ているような光の笑い顔を見ていると、無気力症候群という病気であることが信じられなかった。
しかし、全てを受け入れ、どんなに時間がかかっても、もとの元気な光にしない限り、家族の再生もあり得ない思った。光にとってこの風景、海辺で母親と遊んだこと、おにぎりを食べたこと、そして住いでの暮らし、ひとつひとつがいい記憶となって残っていって欲しい。そのためには、自分もこの街を、この環境を好きになろうと思った。
歴史を含めたこの風土や風景を好きにならないで、どうして子供にいい記憶を残してやることが出来るのか。
マンションを見上げながら咲子は、今までと違った生き方が出来るような、そんな第一歩が今夜から始まるような気がした。
目を閉じて、胸いっぱいに、潮の匂いがする息を吸い込んだ。
目を開いたら、光が笑っていた。
完
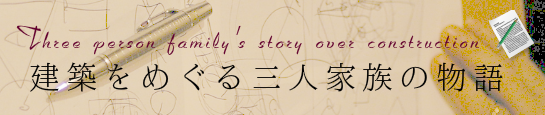
 第23章 幻想
第23章 幻想