横山 彰人 著
第15章 引越し
引越しの前の一ヶ月は、目の廻るような忙しさだった。リフォームの打合せ、引越しの準備や整理、引越しセンターの見積り、マンションの引渡しまでの事務手続き、そして近隣の挨拶まで、一切咲子一人で行わなければならなかった。
武夫は年度末という会社が忙しい時期にぶつかったせいもあるが、家のことはお前に任せてあると言わんばかりに、日曜日の休みの日ですら、引渡しの立会や工事中のマンションにも一度も顔を出さなかった。咲子はかなりストレスも感じ、武夫に対して内心腹も立った。マンションの購入代金の半分以上を咲子の父親が出し、購入決定まで殆んど自分が動いた事に対して何の感謝の言葉もなかった。内心は理解してくれているだろうが、それでも言葉で言って欲しかった。そして家族が過す大事な住まいを、仕事が忙しいとはいえもっと大切に考えてもらいたかった。
疲れだけは確実にたまったが、ストレスがたまったのは咲子ばかりではない。マンション購入を決めて探し始めてから、引越しするまでの期間は、光にとって0歳(五ヶ月目)から一歳九ヶ月の間で、その間ほとんど咲子はマンションの事で頭がいっぱいで、振り返ると光の育児という面では十分手をかけることが出来なかった。そのことも分っていたが、早く良いマンションを購入することは光のためなんだと、今思うと自分自身に言いきかせていたように思う。精神的に、一生一度の家を購入するという、しかも自分一人で決めなければならない追い込まれたような気持ちと興奮状態で、光のことを考える余裕もあまりなかった。
住んでいる社宅もどうせ引越すという気持ちが先立ち、部屋の中はダンボール箱や片付け途中の物などが置かれ、光がハイハイする場もない。光は以前は家中ハイハイをしながら機嫌良く、「バケバケ」とニコニコ笑いながらおもちゃと遊んでいたが、物や荷物が置かれてからはあまり笑わなくなった。そのことも咲子は気になっていたが、早くマンションが決まって引越しすればすぐ治ると考え、その為にも早く見つけなければという思いの方が先に立った。
光を連れて買い物に行くと、商店街のお肉屋、八百屋、魚屋さんなどのおばさんや店員さんは、買い物のたびいつも光を可愛がってくれた。引越しの挨拶に行くと、八百屋の咲子の母と同じ歳のおばさんは、名残を惜しみ光を抱き上げ頬ずりをし、「光ちゃん、お別れなんておばちゃん寂しいね」と涙ぐみ、「光、おばちゃんにバイバイ、またね、って言って」光は何も分らず、「バイバイ、バイバイ」とニコニコ笑って、手を振って手足をバタつかせていた。
「おばさん、色々お世話になりました」社宅の奥様達とは神経疲れる毎日であったが、商店街の気さくな人達との会話がどれだけ癒され心の救いであったかと思うと、涙がこみ上げてきた。
みんな良い人で正直別れたくなかった。引越す先のマンションでもこんな人間関係が築けるだろうか。今度はマンション内の人達とも仲良くしたい。光の遊び友達も出来るだろうか。考えれば考えるほど、自分でもおかしいくらいに期待と心配が交差した。
結婚して子供が生まれ、迷いながら子育てをし、子供のために家を探し、近隣の付き合いから引越しまで振り返ってみると、全て咲子一人で背負ってきた。武夫は確かに優しく誠実で仕事一筋で、夫として不服はないが子供の教育や子育て、家の購入といった家族の歴史の中の大事な場面に、いつも夫はいなかった。これからも光の学校や進路などの重要な場でも、全て一人でやらなければならないのだろうか。そんなことを考えると、とても気が滅入った。
引越しの日が決まり、改めて社宅の部屋を眺めると、新婚時代から光が生まれ、そして今日まで幸せを育んでくれたこの部屋、この匂い、窓から見える景色、光を抱いて武夫の帰りを待ったベランダ、全てが懐かしくいとおしく、感謝せずにはいられなかった。
二月上旬引越しの日、ようやく荷物をほどきホッとした時には、もう夕暮れ近かった。武夫は光をあやしながら部屋で整理をしていると、「見て見て、武ちゃん、こっちへ来て」
とベランダで呼ぶ声がしたので、光を抱いて急いでベランダに行き、咲子の指差す彼方を見ると、海の色が金色に染まりその小さなさざ波が美しく輝き、その波の中をモーターボートがキラキラとしぶきを上げながら夕陽に向って走っているのが見えた。そしてその向こうには、冬の澄んだ空にオレンジ色の太陽が遠くの山脈の中へ沈むところだった。
咲子に抱かれた光も、生まれて初めて見るであろう海の夕陽をじっと見つめていた。
夕陽が新しいこの地で家族の新しい生活を祝福してくれているようだった。
咲子は、今日の感動と幸せを一生忘れないと思った。
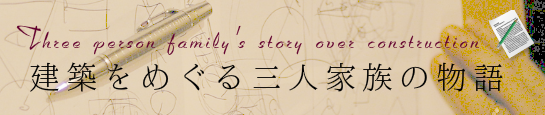
 第14章 リフォーム
第14章 リフォーム