横山 彰人 著
第20章 人工の街並
様々な思い違いや思惑違いによってストレスは蓄積された。
ストレスのはけ口は、まずテレビ。 朝起きてテレビのスイッチを入れて武夫を送り出した後は、光に教育用のビデオを見せる以外は、殆んど一日中つけっぱなしにしていた。先生の言う通りだった。そして、パソコンのネットオークションと携帯メール。これは光の衣類をオークションで買っているうちにはまってしまい、昼ごはんを与えるのも忘れるほど熱中する日も多かった。武夫の帰りが遅く疲れてもいるので、話したい事が沢山あるのに話も出来ない日の方が多く、携帯で会社時代の友人や同級生と話したり、メールのやり取りが増えていった。最初は悪いと思いながら、食事をさせながらも片手でメールを打っていたが、やがてあまりそのことも気にならなくなった。
憧れの高層マンションで、ゆったりと時間が流れ、夕陽を見ながら一日の締めくくりをすると思い描いていた生活とは程遠く、何かに追われるような毎日を送ることが多かった。
感情の起伏も激しくなり、気がついたら光を怒鳴りつけていることもあった。引越しの挨拶状では、是非遊びに来て一度素晴らしい眺望と夕陽を見に来て下さいと付け加えていたが、誰も訪れる友人はいなかった。都心から遠いのだ。二回以上乗り継いで来ても、食事をする所はせいぜいファミリーレストラン。自慢の夕陽を見て貰おうとすると一日がかりだ。友達が来なくて当然なのだ。
確かに駅に近く買い物が便利という条件には合っていたが、コンビニや大型スーパーがあるだけで、人と人の心が通い合う以前のような商店街を期待していただけに、寂しかった。駅にしても、販売図面では歩いて十五分と書かれていたが、女性の足では二十分はかかった。バスの本数は多く便利ではあるが、武夫が帰る十時過ぎは少なくなり、結局歩くかタクシーとなり、その分体の負担とタクシー代も増えた。
駅からマンションまでの道路には、幹線道路特有のどこでも同じような光景が広がる。大型車がスピードを出して行き交い、ガソリンスタンド、ファミリーレストラン、中古車販売店、そして大きな駐車場付きのディスカウントショップなどが並ぶ。初めてマンションを見に来たとき新鮮に映った街も、よく見るとどこの都市の郊外にもある同じような景色であった。
一本道路を入ると住宅地で、整備された道路沿いに住宅展示場のようにパステルカラー色の輸入住宅、ミニホワイトハウスから瓦屋根葺の「純和風」調の住宅など、様々な形と色の住宅が雑然と建ち並んでいる。整備された歩道には、規則正しく街路樹が植えられている。ハナミズキの樹だろうか、春には白や薄桃色の可憐な花が咲き、夏には葉が茂り木陰をつくるだろう。しかし歩道沿いに並ぶ家々は、ブロック塀で囲われ防御の姿勢だけが目立ち、まるで心も閉じてしまっているように見える。
最近の風潮の手入れのかかる樹木や花を敬遠するのか、庭に樹や花を植えている家は殆どない。分譲時期が同じだから購入価格や年収、そして子供の年齢も含め家族構成すら似ている。そんな均質化された住宅地の日中は、朝夫達が出勤してしまうと、殆ど人通りが無い。
京都の西陣や渋谷の住宅地に住む人達は、年齢層も職種も雑多で様々な人が様々な時間帯を行きかっていた。そんな場所で暮らした咲子は、目の前に広がる無機質な住宅地は、好きになるどころか正直とても疲れた。
そして咲子の目からは、それは異様な光景としか映らなかった。この街と風土に愛着が持てるだろうか。咲子は自信が無かった。
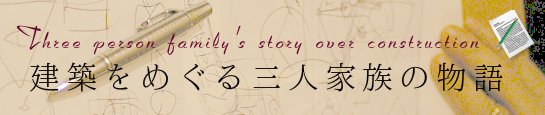
 第19章 マンション...
第19章 マンション...