横山 彰人 著
第4章 新婚の家
この新入社員歓迎会を機に二人は一ヶ月に一度の割合で会い、食事をしたり映画を見たり、日曜日には鎌倉などにも足をのばした。
鎌倉に行った時は、必ず夕方には「江ノ電」に乗って稲村ヶ崎で降り、七里ヶ浜から伊豆半島に沈む夕陽を見るのが定番となった。
浜辺にある大きな石に腰をかけて、陽が沈むまで黙って見つめていた。そんな時間と空間を幾度も共有するにつれ、もしかしたら結婚するかもしれないという予感を感じていた。
会う回数が一ヶ月に一度が二週間に変わり、二週間が一週間になり、男と女の関係になるまで時間はかからなかった。
そして、武夫からプロポーズされた時もあまり驚かなかった。
歓迎会で初めて会って一年、親に相談もせず受け入れた。
二人が結婚して初めての住まいは会社の社宅で、鉄筋コンクリート四階建ての二階で、小さめの3DKだった。築四十年も経っているが年数の割にしっかりしていた。会社は歴史が古く旧財閥系なので、戦前から都心に幾つかの遊休地を持っていて、社宅もそんな土地に建てられたものだった。
JR渋谷駅から歩いて十五分ほどで、戦災で焼けなかった数少ない一角のせいか緑も多く、商店街には古い昔からの店も残っていて、京都で育った咲子は親しみを覚えた。
周辺には美術館や能楽堂やお洒落なブティックもあり、日曜日の夕方は二人で原宿や代々木公園まで足をのばしたり、空気が澄んだ日の夕暮れは、わずかに光る星を数えながら散歩を楽しんだ。
「こんなところに家を持てたらいいね。小さなマンションでもいいから」
「ここは都内でも一等地だからマンションもすごく高いし、俺の給料では無理だよ。だいいち、子供も育てられないほど小さなマンションじゃ意味無いよ。うちの会社の人は、持家の場合通勤時間一時間半から二時間が普通だし、今度家を買った課長は、宇都宮から新幹線通勤だぜ。少し残業すると家に帰るのが十二時過ぎと言ってたよ」
「毎日武ちゃんの帰りが十二時過ぎなんていややわ」
「だって、ここあたりに仮にマンションを買えたとして、おまえの好きな夕陽なんて見れないぜ。マンションから夕陽を見るのが夢だったんじゃないの」
「あ、そやね、肝心なこと忘れていたわ」
そんなたわいのない話に咲子は幸せを感じ、そしてそんな何気ない会話を、いつまでも心に刻んでおきたいと思った。
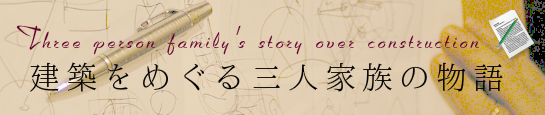
 第3章 記憶の原風景
第3章 記憶の原風景