横山 彰人 著
第18章 生活動線が遮られた家
振り返ると、異常は引越してから二ヶ月目頃から始まっていた。最初の兆候は、社宅にいる時は日中殆んど泣かなかった光が、引越してからしばらくして盛んに泣くようになった。その泣き方も目が落ち着かなく、不安げでヒステリックだった。
原因の一つは先生が言われたように、急に環境が変わったことや、部屋の構造であり生活動線によるものであることは明らかだ。
それは、咲子が最初に心配していたことが的中したと言ってもいい。
このマンションは、リビングダイニングルームのほか、六畳と七畳の洋室が二部屋と、六畳の和室の3LDKで、和室はリビングルームとつながっている。南西の角部屋なので、どの部屋にも太陽の光が入り、願ってもない環境ではあった。この点もマンションを決める要素の一つであり、仮に将来売却する場合にも、父親から言われた付加価値を高める条件に沿うものでもあった。
しかし生活動線という意味では、望んだ間取りとは全く異なった間取りだった。
玄関から入るとリビングルームに行くには、廊下を五メートル程歩き、九十度左に曲って六メートル程行った突き当りに、リビングルームのドアがある。将来光の部屋にしようとしている部屋と夫婦の寝室は玄関寄りにあり、どちらもリビングルームからは遠く、気配は全く分らないし声も届かなかった。
キッチンはダイニングとは切り離された独立形なので、料理をしている時は武夫や光がリビングで何をしているか全く分らない。
特に日中咲子がキッチンに入り光がリビングで遊んでいても、咲子の姿が確認できないので姿を追っていつも不安な表情をし泣き始めた。また、以前のようにテレビを同時に見ることが出来ないため、会話に参加することも出来なくなった上、光が寝て武夫が寝室に入ってしまえば、咲子一人がキッチンに取り残されてしまい孤独感が募った。
こうした環境と間取りの変化は、光に大きな影響を与えずにはおかなかったのだろう。さらに親子の触れ合いということでは、夫婦にとっても光にとっても、予想外の出来事が起ってしまった。家族三人で一緒の寝室で寝ることが出来なくなってしまったのだ。
それは咲子の失敗で、購入したベッドが寝室に入らず現在寝室には武夫が、咲子と光が和室に寝るという、極めて予想外な事態を招いてしまった。それは咲子の早とちりで起ったことだ。前からベッドで寝たいと思っていたので、散歩がてらに武夫と家具のショールームを見た時どうしても欲しいベッドがあった。
今購入しても引越しまで預かり、その日にマンションに配達してくれるという物分りが良さそうな店員の言葉につられて、強引に予約をしてしまった。セミダブルとシングルベッドの二つを光が成長するまで寄せて三人で寝るつもりだった。武夫は、「引越してから買っても遅くないんじゃないか。ベッドを置いたらどれだけのスペースが余るか分らないじゃないか。寝室にはベッドの外に置かなくてはならないものが、もっと出てくるだろうし」とちょっと注文をつけたが、「引越した日から快適な睡眠をしたいんよ。また武ちゃんと休みの日に渋谷まで出てくるのしんどいわ」と言って押し切った。
ベッドは自己資金から出す事になるが、マンション購入代金の大半を咲子の父親から出して貰い、マンション選びから引越しまで全て咲子にまかせきりという負い目もあり、それ以上言えなかった。
ベッドカバーは、咲子が寝室の壁に貼った壁紙の色と同系色の、淡いベージュの花柄を選んだ。そして、「インテリアは壁や天井の壁紙の色、窓のカーテン、そしてベッドカバーを含めて、つまりトータルコーディネーションが大切なのよ」と、一席ぶった。
しかし引越しの日運送屋さんが寝室から、「奥さん、奥さん」と大きな声で呼ぶので行ってみると、なんと二つのベッドが寝室に入らないのだ。さすがに咲子は青くなった。
原因はショールームの大きな空間で見たので、このぐらいは入るだろうと安易に想像してしまったこと。またマンション特有の鉄筋鉄骨コンクリート構造なので部屋の角に柱があることを、すっかり忘れてしまって、ベッドは柱が邪魔してどうしても入らなかった。結局自分で招いたミスをどこにも持っていくことができず、苛立った。
しかし今更返品する訳にもいかず武夫の手前、「そのうち、お父ちゃんからリフォームの費用を出してもろて壁を移動して部屋を広くするさかいに、それまでシングルベッドは光の部屋に置いておこう」とつとめて冷静な口調で言った。
そして武夫は寝室でセミダブル、咲子と光は、リビングルームの一角の和室に布団で寝ることになった。今まで親子三人が川の字になって寝ていたのに、いきなり咲子と二人だけで寝ることに、光は言葉を話せないが驚き不安だったに違いない。以前会社からどんなに遅く帰っても頭をなでたり頬ずりをしたりしていたが、寝室が別になってからはそんな触れ合いも無くなった。
武夫は何も言わなかったが、別々に寝るようになって、微妙に夫婦の空気も変わったように思う。そして間違いなく社宅の時に比べ会話が減ったことは、お互い気がついていた。この件については、小児科の先生に恥かしくて言えなかった。
しかし先生の話を聞いているうち、社宅では親子が川の字に寝ていたのに今はバラバラということは、案外重要なことではなかったかと今になって思い、自分の軽率さを悔やんだ。
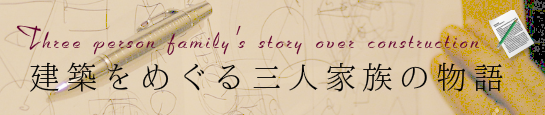
 第17章 何が間違い...
第17章 何が間違い...