横山 彰人 著
第9章 マンション探し
マンションを選ぶには、とにかくいろんなマンションに足を運び見ることが大切だと聞いて、咲子はこの一ヶ月の間、頼んでいる不動産会社の担当者吉川と、五軒ほど光をつれて見て歩いた。五軒のうち、武夫と一緒に行ったのは一度だけ。仕事が忙しく、継続して見に行くことは出来ないのだ。
咲子が見学を通じて分ったことは、確かに吉川が言った通り足を運び見ることは、たとえ条件が合わなくても無駄ということはなかった。気に入らなかったマンションでもどこか勉強になるところがあるし、第一目が肥えてくる。
どこが受け入れることが出来ないかが分り、その事が次の物件選びのベースになってくる。咲子はそれが序々に分ってきたし、もともとインテリアが好きでその分野に進みたかったこともあって、それなりに楽しかった。
武夫は仕事が忙しいということもあったが、継続して見ていないので咲子と比べ、住まいの情報量や知識の差も大きくなって話が合わなくなったことも、熱が入らない原因のようだった。結局マンション選びは咲子に全てまかせてしまうことになった。
担当の吉川は、「どこの御主人もみんな同じですよ。奥様の方が住まいのこだわりや知識も御主人より上で、結局は奥様まかせがほとんどですよ」
確かに武夫に限らず、男は女より住まいに対して淡白かもしれない。
男が淡白というより、家で一日の大半を過し、家族の健康を守るキッチンや収納スペースを含め、女性の方が住まいに対して思い入れもこだわりも深いとも言える。
男は結局、会社までの通勤時間、寝る部屋やリビングの広さくらいしか主張できないのだ。
しかし、かつて家は男のものだった。咲子の父親にしても、床の間にどんな掛軸を掛けるか、どんな季節の花を飾るか、家の補修や増築にしても母に口出しはさせなかったし、家に対してこうあるべきだという一言も持っていた。
そんな家庭で育った咲子は、時代が変わったとはいえ、武夫には一生一度の買い物である住まいには責任を持って欲しかったし、これから家族三人で暮らす住まいだからこそ、二人で決定したかった。
武夫は、「マンションなんて必要な部屋数さえあればどれだって同じだよ、咲子にまかせるよ」と、開き直ったような言葉のくり返しだった。
このまま咲子一人の決断で決めた時、何か問題があった場合自分一人に責任を押しつけられてしまうのではないかと、そのことも不安だった。
「それにしても奥様の条件が厳しすぎます。これだけの条件にピッタリ合う物件なんて、なかなか見つかるもんじゃありません」
と吉川は、案内したマンションが条件に合わなくて断るたびに、同じセリフを言う。
咲子はマンション探しを始める前に、準備勉強のため近くの図書館から二冊の本を借りた。一冊は収納とインテリアの本、もう一冊は建築家の書いた「間取り」についての本で、家族コミュニケーションの取りやすい間取りと取りにくい間取りが、事例をもとにわかりやすく書かれていた。パラパラページをめくると、明治の文豪幸田露伴の言葉を例に引いて、〝人間は住まいの構造や間取りによって、行動や精神が大きく影響される〟と引用されていたことが気にかかって借りることにした。
咲子にとっても、今の社宅の間取りが玄関から丸見え以外気に入っていたから、出来れば家族がどこにいても気配が分り自分達の暮らしに合った、住みやすい間取りの住宅を選びたかった。
整理が苦手な咲子は、出来る限り収納も欲しかったし、洗面カウンターもホテルのように長く大きく小物もたくさん入るのが夢だった。
また、駅に近く買い物に便利、武夫の会社へドアツードアで一時間以内、光のために有名幼児教室が近くにあること、そして咲子の父親が言っていた、売る時にすぐ売れて資産価値が目減りしないマンション。
その後、父親の要望はもうひとつ加わった。
「咲子、ワシが母さんと上京した時泊まれる畳の部屋で六畳以上やで。それに床の間は絶対なきゃいかん」
いまだ古い伝統や風習が生きている京都では、和室に床の間が無いことは考えられなかったのだ。
要望事項はこれだけでは終わらない。なんといっても絶対に妥協できないことは、マンションのベランダから美しい夕陽が見えることだった。パーティーが出来るリビングとオープンキッチン、そんなリビングリームからも夕陽が見えることは、高校時代から思い描いていた青春の夢であり、ステータスでもあった。
購入するにあたって、咲子なりにゆずれない要望事項だけでも結構なボリュームになった。このほか、将来インテリアの勉強をするための専用小部屋も是非とも欲しかったが、当面子育てに追われることは分っていたので加えなかった。
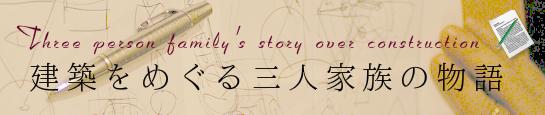
 第8章 川の字の空間
第8章 川の字の空間