横山 彰人 著
第5章 社宅の不満
社宅の環境と住み心地はとても満足していたが、咲子には武夫に言えない二つの不満があった。その不満は最初は感じなかったが、少しずつ蓄積し、今では大きなストレスになっていた。
それは、同じ会社の人が住む社宅ゆえの、人間関係によるものといっていいかもしれない。
ひとつは、毎日の買い物や日曜日二人で散歩に出る時も、奥様方の視線がいつも気のせいか感じられ、気が抜けなかった。
夫の上司やおしゃべり好きな奥様には特に気を使った。
社宅に入った頃、入れ替るように引越していった家族がいたが、その後の話によると、その奥様が午前一時頃、男の人に送られて帰ってきたところを窓から見ていた人がいて、その噂が噂を呼んで結局いたたまれなく、引越していったという。一種のいじめの行為であるが、夫の出世や身につけているブランドの数から、ゴミの出し方まで噂の対象になった。誰もが話の標的にならないよう振舞う空気があり、社宅ゆえの独特な雰囲気があった。商家でおおらかに育った咲子には、神経が擦り減るような毎日を過ごした。
もうひとつは住宅の構造で、社宅の間取りには全く不満が無かったが、玄関ドアを開けると家の中が全て見えてしまうことだった。社宅でなければインターホンだけで事済む場合も多いが、様々な連絡や何かにつけ声をかける奥様が多く、玄関ドアを開けない訳にいかないことが苦痛だった。
咲子が育った家は和室が中心で、必要なものはすぐ手の届く所に置く習慣があった。
一見雑然としていたが、恥かしいという気持ちは全く起こらなかったし、和室の押入のほか、年中行事で使うものや季節以外の物は、離れの納戸に収納しておくことができた。
しかし、社宅は収納のスペースが少ないので、部屋をスッキリ見せるには収納の技術が求められ、咲子は苦手だった。
その苦手な習慣は結婚しても変わるわけはなく、勝手にリフォームも出来ず、恥かしい思いを幾度となくした。その事が奥様達の話題に上らないかといつも気になって仕方がなかった。
この二つのことは、女には分り男には理解してもらえないことでもあった。何でも武夫に話している咲子だったが、自分自身の性格のことでもあり、話もできずストレスの原因になった。
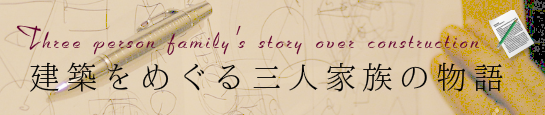
 第4章 新婚の家
第4章 新婚の家