横山 彰人 著
第22章 原因
長野の父親に、マンションを購入し引越しをしたと報告したら、京都の方からお金を出してもらったのかと露骨に言われ、しどろもどろの返事をしたら、父親は状況を察したらしく、
「武夫、長男であるお前が女房の実家に金出して貰って家を買ったなんて、田舎に来て親戚や周りの人に絶対に言うな」それだけ言って、電話を切ってしまった。
父親は長男である自分に何を言いたいか、よく分っていた。このショックは大きく父親の声がずっと耳に残って癒えなかった。
また、咲子の父親の電話に出るたび何か卑屈になってしまい、以前のように普通の気持ちで話せなくなってしまった自分自身が嫌だった。そんな思いが、つい口に出てしまったのだ。
咲子は武夫の怒りの矛先が父親に及んだことに、我慢ならなかった。
「武ちゃん、それはあんまりじゃない。私の事は何言うてもええけど、お父ちゃんを悪く言うのはやめてちょうだい。資金を出してもらった件でも、みんな武ちゃんが了承したさかいに出してもらったん違う。和室の件だって立地条件だって、このマンションに決定するまで仕事仕事で何も協力しないで全部私にまかせて、後でそんな事言うなんて男として卑怯と違う」そこまで言うと咲子は、無性に悔しく涙が溢れて止まらなかった。
子育てに感謝の気持ちやいたわりの言葉をかけて欲しいとは思わないが、せめて子育ての厳しい現実を少しでも分って欲しかった。光が生まれて初めて分ったことだが、自分達が生まれ育った時代と今では、子供を取り巻く環境が全く異なってしまい、母親一人の力ではどうにもならない限界があるということを。
光がこうなったことが全て咲子の責任なのか、武夫には全く責任が無いのか。
「武ちゃん、もう一言だけ言わして。確かに光の病気は、私がいたらなかったことが原因かもしれない。でも父親の役目って何? 仕事が忙しいのは分るし、私達のために頑張って働いてくれているのも分るし、感謝もしている。だから私は、夜疲れて帰ってくるから少しでも休ませてあげようと思って、光のことで相談したいことや話したいことがあっても、我慢してきた。だっていつだったか、公園で光の動作が遅くて、少し年上の子供から砂をかけられ倒された時、私ショックで夜あなたに話をしたくって、でも遠慮しながら話始めたら、疲れているから明日にしてくれって、話すら聞いてくれなかった。
そんなことが何回かあって、それからあまり話さなくなった。私にしても、渋谷から移ってきて友達も無く、昔の友達とメールやせいぜい電話で紛らわせていたけど、そんな悩みも聞いて欲しかった。光のことばかりでなく、私達夫婦のことだって、話さなければならないことが沢山あるのと違う? このままじゃ光ばかりでなく、私達夫婦だっておかしくなってしまうような気がするの」今度はしっかり武夫の目を見て話した。
武夫は結婚して初めて語気を荒げて自分に向けた「卑怯」という言葉と、自分の知らない子育ての日常の中で、精神的に追い詰められている状況が、咲子の激しい言葉と表情から分ってたじろんだ。
自分が会社で仕事に没頭している間に、家庭を取り巻く状況が確実に変ってしまったことを、咲子の目が語っていた。何かを変えなければ、このままでは何か大切なものを失ってしまうような気持ちがふとよぎったが、言葉は心とは全く別なことを話していた。
「俺は今、会社の中で生き残れるか残れないかのところで、毎日必死なんだ。本当は家に会社で処理できなかった仕事を持ち込んでもやりたいぐらいなんだ。部長も俺に期待しているし、精一杯仕事をやって体もクタクタなんだ。
みんな家族のためじゃないか。家の事、子供の事、みんな女房に任せて何が悪い。どこの家庭も同じじゃないか」咲子は武夫の話を聞きながら、二人の間の絆がだんだん離れていきつつあることを感じた。
「武ちゃん、もう一度考えてみて。仕事が大変なことは分るけど、もっと光と私を見て欲しいの。光の目、光の行動、そして私の日常。全て知って欲しいとは思わないけど見る努力をして欲しいの。そして一緒に考えて欲しいの。私達の育った子供時代の環境と、どれだけ違っているか知って欲しい」咲子は必死だった。それは子育てに自信も方向性も失った、自身の悲鳴に近い叫びのような言葉だった。
武夫は、そんな咲子に次に返す言葉が出てこなかった。仕事を理由にいくらでも弁明することは可能だったが、訴えるような言葉の前に何も言えなかった。
光の中で起きている無気力症候群という病気が、いつから芽ばえているかを咲子の言葉から読み取ると、ちょうど自分が会社の中で仕事に追われ、心に余裕を失ってしまった時期と重なっているように思われた。心の余裕の無いままこのマンションに引越し、毎日一時間三十分以上の通勤時間の疲れも重なり、週二回の自宅での食事も出来なくなり、一日の出来事もお互い話さなくなってからのような気がした。
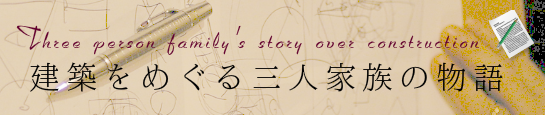
 第21章 他人の顔
第21章 他人の顔